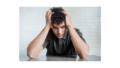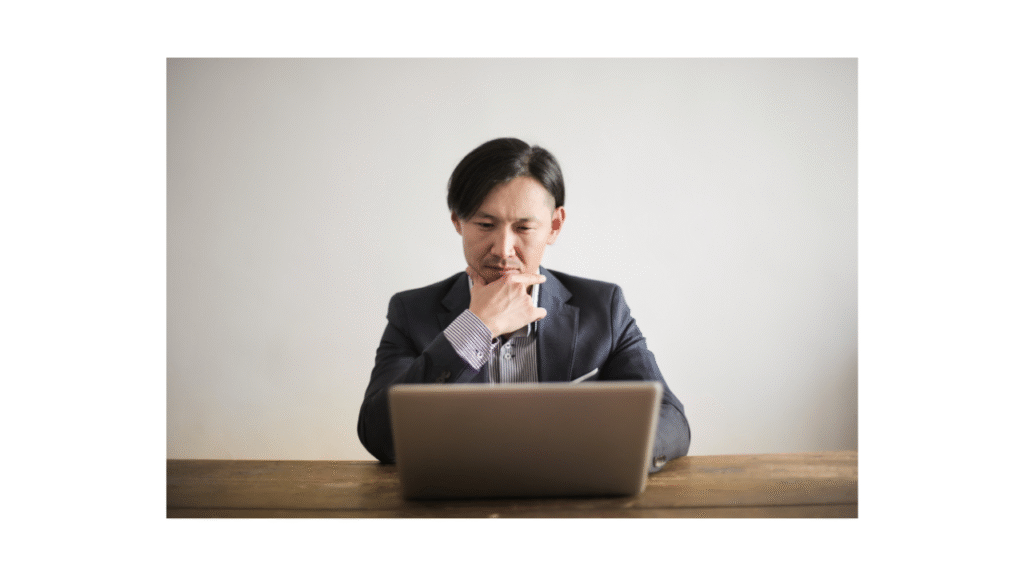
はじめに
こんにちは。
この記事は、これから新NISAを活用して高配当株投資を真剣に始めようとしている方に向けたものです。
2024年から始まった新NISAは、年間最大360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)という大きな非課税枠を使えるのが魅力です。
この制度を使って高配当株投資を行うと、どんなメリットがあるのか。そもそもNISAと高配当株の相性はどうなのか。そして、なぜ私があえて新NISAで高配当株を選んだのかについてもお話しします。
結論から言えば、「相性は悪くないが、最適解とも言い切れない」というのが私の率直な感想です。
でも、それでも私はこの組み合わせを選びました。その理由も包み隠さず書いていきます。
そもそも配当金とは
株式を保有していると、企業が利益の一部を株主に還元してくれることがあります。これが配当金です。
例えば、1株あたり100円の配当がある株を100株保有していれば、年間で1万円の配当金が受け取れます。
分配金との違い
似た言葉で「分配金」というものがあります。これは主に投資信託やREIT(不動産投資信託)から支払われるお金で、配当金と似ていますが、必ずしも利益だけから支払われるわけではありません。場合によっては元本を取り崩して支払われるケースもあります。
つまり、「分配金が多い=運用が順調」とは限らないということです。
NISAで高配当株を買うなら「成長投資枠」一択
新NISA制度では、個別株式に投資できるのは成長投資枠のみ。年間240万円まで非課税で投資できます。
一方、つみたて投資枠(年間120万円)は長期積立専用で、投資信託やETFなどに限定されます。配当金狙いの個別株投資をするなら、成長投資枠の利用が必須です。
NISAなら配当金は非課税
通常、配当金には約20.315%(所得税+住民税)の税金がかかります。
例えば年間10万円の配当金をもらっても、実際の手取りは約8万円です。
しかし、NISA口座で保有していればこの税金がゼロに。つまり10万円がそのまま受け取れます。これは長期的に見ればかなり大きな差になります。
非課税で受け取るための設定に注意
ここで落とし穴があります。
配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定しないと、非課税にならない場合があるのです。
郵便局受取や銀行口座振込を選んでしまうと、課税される可能性が高まります。必ず証券口座で受け取る設定にしておきましょう。
高配当株とNISAの相性は本当に良いのか?
高配当株の定義
一般的に、配当利回り3〜4%以上の株は「高配当株」と呼ばれます。
株価が安定していて、毎年安定した配当を出している企業が理想です。
実はインデックス投資のほうが有利な場合も
高配当株投資は魅力的に見えますが、複利効果という面ではインデックス投資に劣る場合があります。
理由は、配当金を再投資する際に税金が引かれるからです(通常口座の場合)。課税分だけ元本が減るため、雪だるま式の資産拡大がやや鈍くなります。
一方、インデックスファンドは配当を自動再投資する仕組みを持っており、課税によるロスを最小限にできます。新NISAの非課税枠で運用すれば、値上がり益も全額非課税です。
それでも私が高配当株を選んだ理由
ここまで読んで「じゃあ高配当株はやめたほうがいいのでは?」と思う方もいるでしょう。
しかし、私はあえて高配当株をNISAで運用しています。その理由はシンプルです。
「今すぐ使えるお金を増やしたかったから」です。
我が家にはまだ小さい子供がいて、旅行や外食、習い事などの支出が多い時期です。
将来の資産拡大も大事ですが、「今」家族と楽しむためのお金も大事。
そこで、資産のうち4分の1を成長型投資(インデックスなど)に回し、残りを高配当株で運用することにしました。
配当金はほぼ全額、家族との時間に使っています。この方針が正解かはわかりませんが、「株の利益で旅行に行く」という経験はお金以上の価値があると感じています。
高配当株投資で意識していること
- 自己資本比率60%以上の企業を選ぶ(財務健全性)
- 過去5年以上減配なしの実績を重視する
- セクター(業種)が偏らないように分散する
- できれば30銘柄以上でリスクを分散
まとめ
高配当株とNISAの相性は「良くも悪くもない」というのが正直なところです。
資産拡大を第一に考えるなら、インデックス投資のほうが効率は高いでしょう。
しかし、「今の生活を豊かにするキャッシュフローが欲しい」という目的なら、高配当株+NISAは強力な武器になります。
NISAの成長投資枠を使えば、税金を気にせず配当を受け取れます。
その配当を生活の潤いに使うのもよし、再投資してさらに資産を増やすのもよし。
大切なのは、自分の目的とライフスタイルに合った投資戦略を選ぶことです。