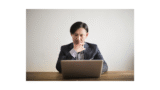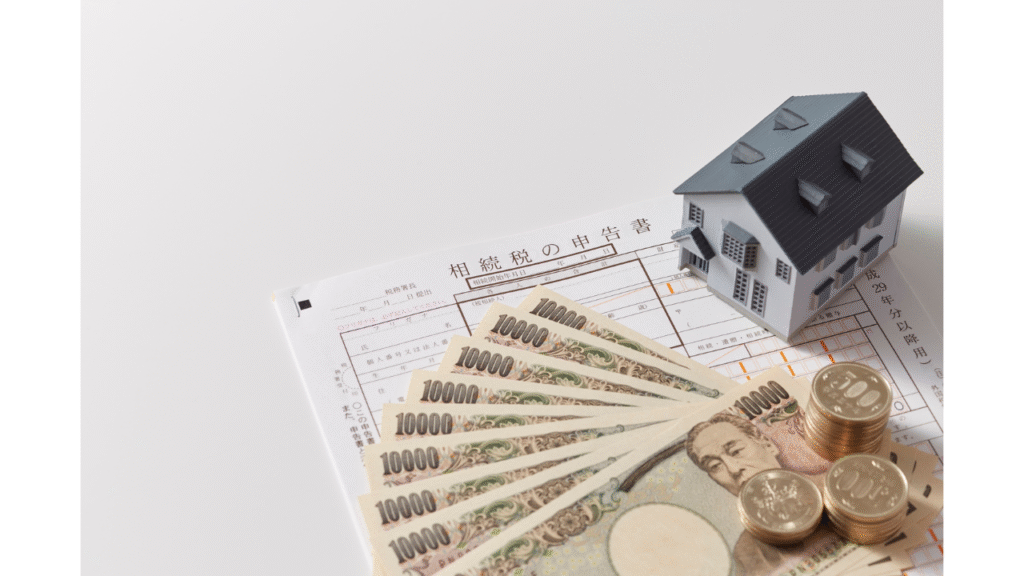
こんにちは。今日は「株式投資を始めた人なら必ず押さえておきたい」けれど、意外と見落とされがちなテーマを取り上げます。
それは 配当金の受け取り方 です。
株を買ったことがある人なら「配当金が入金されました!」というメールを見たことがあるかもしれませんね。でも実は、その配当金の受け取り方法を間違えると NISAの非課税メリットが受けられない という落とし穴があります。なんとなくで設定していたら課税されてしまう可能性があるのです。
この記事では、配当金の仕組みと受け取り方法の違い、なぜ「株式数比例配分方式」が大事なのか、そして注意点をわかりやすく解説していきます。
そもそも配当金とは?
まずは基本から。
配当金とは、企業が出した利益の一部を株主に還元する仕組みです。
例えば、1株あたり100円の配当を出す会社の株を100株持っていたら、年間で1万円の配当金を受け取れる、というイメージですね。
投資信託などから支払われる「分配金」とよく混同されますが、あちらは元本を取り崩す場合もあり、性質が少し違います。今回のテーマはあくまで 株式の配当金 に絞ります。
配当金の受け取り方法は4種類ある
意外と知られていないのが、配当金の受け取り方法が複数あることです。大きく4つに分けられます。
- 株式数比例配分方式
→ 証券会社の口座に自動的に振り込まれる方式 - 登録配当金受領口座方式
→ 自分の銀行口座を登録して、そこに直接振り込んでもらう方式 - 配当金領収証方式
→ 郵便局に行って受け取る方式 - 個別銘柄指定方式
→ 銘柄ごとに受け取り方法を指定する方式
パッと見、どれでも同じように思えますよね。
しかし、ここに大きな落とし穴があるのです。
NISAで非課税にするには「株式数比例配分方式」が必須!
新NISAで株を買ったとき、誰もが楽しみにするのが「非課税で配当金がもらえる」こと。
本来なら配当金には約20.315%(所得税+住民税)がかかりますが、NISAで買った株の配当なら非課税になります。
ところが!その非課税メリットを受けるためには 受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要がある のです。
例えば、銀行口座に直接振り込むように設定してしまうと、税金がしっかり引かれてしまいます。これはつまり、せっかくNISAを使っても「通常課税と同じ扱い」になってしまうということ。
株式数比例配分方式ってどういう仕組み?
「株式数比例配分方式」というのは、シンプルに言えば 証券会社の口座に株数に応じて自動で配当金が振り込まれる方式 です。
メリットは大きく2つ。
- NISAの非課税が自動的に適用される
→ これが一番大きなメリット。税金を引かれずに全額受け取れます。 - 管理がラク
→ 銀行口座や郵便局で別々に受け取る必要がなく、証券口座内で完結。入金履歴も見やすい。
デメリットはほとんどありませんが、強いて言えば「銀行に直接振り込まれないからまとめて生活費に使う感覚は薄い」ことくらいでしょうか。
もし間違った方法を選んでしまったら?
仮に登録配当金受領口座方式などを選んでしまった場合、どうなるのでしょうか。
- その時点で課税されてしまう
- 後から非課税に修正してもらうことはできない
つまり「気づいたときには手遅れ」というケースが多いのです。
これは非常に残念ですが、制度のルール上避けられません。
ですので、投資を始めたら最初に「株式数比例配分方式」に変更しておくことが鉄則 です。
配当金投資をする人ほど要注意
この設定、インデックス投資一本の人ならあまり気にしないかもしれません。なぜならインデックス投信は基本的に分配金を出さず、ファンド内で自動再投資されるケースが多いからです。
しかし、高配当株投資をしている人は話が別。
毎年まとまった金額の配当を受け取ることになります。その配当金に毎回20%以上の税金がかかってしまうと、非課税枠の恩恵をほぼ無駄にしてしまうのです。
「高配当株×NISA」をやるなら、株式数比例配分方式は必須の設定と言えます。
NISA以外の配当金は課税される ― その後の選択肢
ここまで「NISAで非課税にするなら株式数比例配分方式が必須!」と説明してきました。
ただし、当然ながら 特定口座や一般口座で持っている株式の配当金は課税対象 になります。
通常は証券会社が源泉徴収してくれるので、確定申告不要でそのまま完結できます。
しかし「確定申告」をすることで、場合によっては税負担を軽くできることがあります。
その方法が 申告分離課税 と 総合課税(配当控除あり) の2つです。
申告分離課税にする場合
メリット
- 株の譲渡益(売買益)と損益通算できる
→ 例えば配当金で+10万円、株の売却で-10万円なら、課税額をゼロにできる。 - 損失繰越控除が使える
→ 損を翌年以降3年間まで繰り越して税金を減らせる。
デメリット
- 税率は基本的に変わらない(約20.315%)
- 所得税や住民税を下げる効果はない
つまり「株で損が出ている人」に有効な方法です。
配当金を申告分離にすることで、損益通算して税金を取り戻せる可能性があります。
総合課税にして配当控除を使う場合
メリット
- 配当控除 が受けられる
→ 所得税で最大10%、住民税で最大2.8%を税額から差し引ける。 - 低所得者(給与収入が少なめの人)は実質的に税金が大きく減ることもある。
デメリット
- 他の所得と合算されるので、課税所得が増えてしまう
- 所得が高い人(特に年収900万円以上など)は、かえって税率が高くなり逆効果になる
- 国民健康保険料や介護保険料の算定基準となり、保険料が上がることもある
つまり「比較的所得が低めで、課税所得が一定の範囲に収まっている人」にとっては有利。
一方、年収が高い人が総合課税を選ぶと逆に損してしまうケースが多いです。
具体的にどう判断する?
- 給与所得や事業所得が少なめの人
→ 総合課税+配当控除がお得になるケースあり - 給与所得が高め or 株で損失が出ている人
→ 分離課税で損益通算した方が有利 - NISAで持っている株の配当金
→ そもそも非課税なので申告不要
ここは「人による」ところが大きいので、実際にはシミュレーションしてみるのがベストです。証券会社や国税庁のシミュレーションツールを使うと目安が出せます。
まとめ:NISAと課税口座は別モノで考えるべき
- NISAの配当は「株式数比例配分方式」で受け取り、完全非課税に。
- NISA以外の配当は「分離課税」か「総合課税+配当控除」を選べる。
- 損をしている人は分離課税、所得が低めの人は総合課税が有利になるケースが多い。
投資初心者のうちは「NISA=非課税だから安心」と思いがちですが、課税口座での配当金も含めてトータルで考えることが大切です。