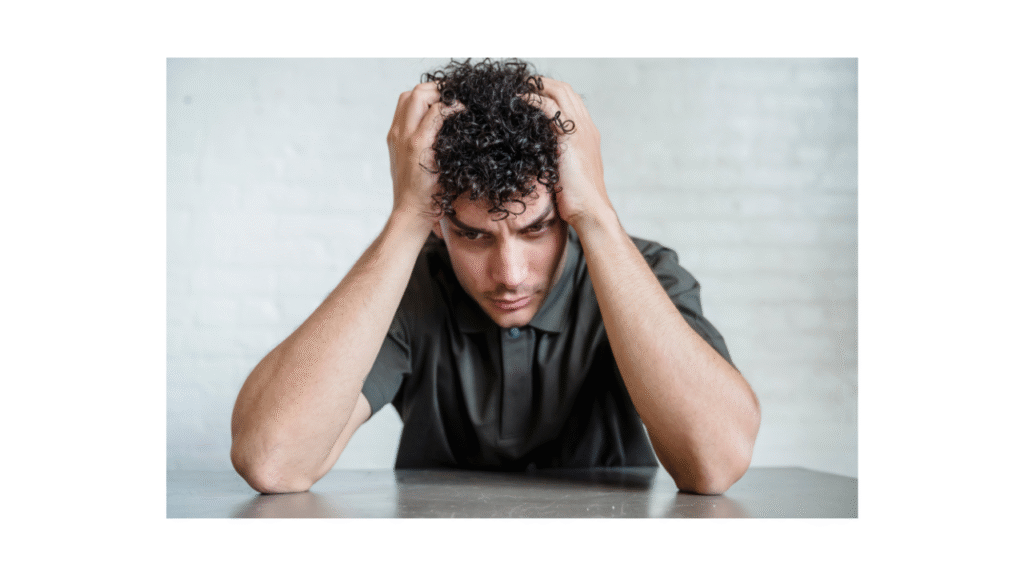
副業解禁やFIREブームもあって、収入源として人気が高い「民泊」。
実は私も真剣に検討したことがありました。しかし最終的に言うと、私は民泊運営を断念しました。
今回は、会社員が副業として民泊をやる際の制度面やコスト構造、そして私自身の働き方との相性を踏まえて「なぜ断念したのか」をまとめてみます。これから副業を考えている方の参考になれば幸いです。
結論:会社員の副業には不向きだった
最初に結論です。
民泊は「時間に融通がきく人」や「専業で取り組める人」には十分チャンスがあると思います。
ですが、会社員の副業としては市場次第でかなり厳しい、と実感しました。
表面的には「手軽にできそう」「不労所得っぽい」と魅力的に見えるのですが、実際には 制度の縛りとコスト構造がシビア で、利益を出すには時間と手間がどうしても必要になります。
制度の壁:民泊法と旅館業法
民泊を始めるには、主に2つの制度があります。
- 旅館業法(簡易宿所営業など)
- ホテル・旅館と同じ扱い
- 年間の営業日数制限はなし
- ただし設備や消防法の基準が非常に厳しく、許可取得のハードルが高い
- 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)
- 規制が緩和されて参入しやすい
- ただし 年間180日までしか営業できない
- ゲスト対応を委託する「管理業者」を必ず入れる必要がある
会社員の副業なら現実的なのは「民泊法」ですが、この180日制限が収益に直結してしまいます。年間フル稼働できない以上、収益モデルをかなりシビアに考える必要があります。
市場相場とコストのギャップ
私が検討した地域では、1泊あたりの相場は 8,000円前後 でした。
「まあまあ悪くないな」と思ったのですが、問題はコストです。
- 清掃費:外部業者に依頼すると1回 8,000円程度
- 運営代行費:売上の一定割合(10%〜が多い)
- 消耗品・リネン交換費用
- 光熱費・Wi-Fi回線
- ローンや賃料(借り物件の場合)
清掃を自分でやれば抑えられますが、会社員が仕事の合間に毎回対応するのは現実的ではありません。結果、「売上=清掃費で消える」 というシミュレーションになってしまいました。
一泊あたり数万円で回せる都市圏や観光地なら事情は違うと思いますが、私が狙ったエリアでは厳しかったです。
実際に試算してみた
では、実際に数字を当てはめてシミュレーションしてみます。
- 宿泊料金:8,000円/泊
- 稼働率:50%(月15泊想定)
売上
8,000円 × 15泊 = 120,000円
ここから費用を引いていきます。
- 清掃費:8,000円 × 15泊 = 120,000円
- 運営代行費:売上の10% = 12,000円
- 光熱費・ネット・消耗品など:20,000円
合計コスト
120,000円 + 12,000円 + 20,000円 = 152,000円
→ 売上12万円 − コスト15.2万円 = ▲32,000円(赤字)
稼働率を70%(月21泊)に上げても…
- 売上:8,000円 × 21泊 = 168,000円
- 清掃費:8,000円 × 21泊 = 168,000円
- 運営代行費:売上の10% = 16,800円
- 光熱費・ネット・消耗品など:20,000円
合計コスト = 204,800円
→ 売上16.8万円 − コスト20.48万円 = ▲36,800円(赤字)
シミュレーションを進めていくと、結局こうなりました。
- 180日の稼働制限
- 清掃費+代行費で売上がかなり削られる
- 稼働率が想定より低いと一気に赤字
「副業で不労所得!」と期待していたのですが、実態はかなりシビア。
フル稼働できない以上、固定費や委託費用が重くのしかかってきます。
将来FIRE後なら「あり」
とはいえ、まったく希望がないわけではありません。
- 時間に余裕があって清掃やゲスト対応を自分でできる
- 旅館業の許可を取り、稼働制限なく運営できる
- 物件を選び抜けば、収益化は十分可能
つまり、会社員の副業としては赤字リスクが高いが、FIRE後の副業としては有力 というのが私の結論です。
まとめ:副業選びは「時間×制度×市場」
今回私は「会社員の副業として民泊は不向き」と判断して断念しました。
しかし制度や収益構造を調べる中で、「FIRE後にもう一度検討したい」とも思っています。
副業として民泊を考えるなら、以下の3つを必ずチェックするのがおすすめです。
- 自分の働き方(清掃や対応に時間を割けるか)
- 市場価格とコストのバランス(シミュレーション必須)
- 制度の制約(180日制限や許可の難易度)
民泊は「時間と制度の理解」が成功のカギ。会社員である今は難しくても、将来の選択肢として検討する価値はあると思います。


