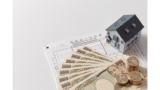こんにちは。今日は、僕が休職中に強く実感した「配当金のありがたさ」について書きたいと思います。
普段はインデックス投資をメインにしている僕ですが、この時ばかりは高配当株の存在に救われました。
休職で収入減、生活費は30万円のまま
休職に入る前、僕の生活費は月30万円ほど。家賃、食費、光熱費、通信費、保険、そして突発的な交際費などを含めて、このくらいで回していました。
しかし休職に入ると、会社からの手取りは25万円程度に。
「5万円の赤字」が毎月積み重なる計算になります。
普通なら貯金を切り崩すしかありませんが、精神的に弱っているときに「毎月減っていく口座残高」を見るのは本当にキツい…。
そんな中で助けになったのが、毎月口座に入金される配当金でした。
毎月の配当金が生活費の3割をカバー
僕の場合、年間配当金は約88万円。
月平均で7万円ほど、証券口座から銀行口座に入ってくる計算です。
この7万円があるおかげで、
- 生活費30万円のうち25万円は給与(有休消化中)
- 残り5万円+突発的な支出は配当金
という形で、赤字をほぼゼロにできました。
「配当金がある=生活費の2割は資産が稼いでくれる」という状況は、想像以上に精神的に楽でした。
毎月のやりくりに追われず、急な出費にも落ち着いて対応できたのです。
インデックス投資は「崩せない」心理的ハードル
一方で、僕が普段メインで積み立てているインデックス投資(S&P500や全世界株)は、こういう時でも崩す気になれませんでした。
理由はシンプルで、
- 将来の資産拡大を支えてくれる柱だから
- 売却=複利の恩恵を削る行為に思える
- 精神的に「生活費に使うお金」ではない
だから、休職中で収入が減った父(70歳)でさえ、「インデックスは売れない」と言っていました。
将来の値上がりを期待する投資は、心理的に「取り崩す対象」にはなりにくいのです。
配当金は「使うためにある」から気楽に使える
配当金の最大の特徴は、現金として振り込まれること。
証券口座に記録される評価額の上下ではなく、銀行口座にリアルに現金が入るので、「自由に使っていいお金」という意識になりやすいです。
実際、僕も配当金で以下をまかなえました。
- 家電の故障による突然の買い替え
- 医療費の急な支出
- 外食や交際費
これをもし「インデックス投資を一部売却して現金化」していたら、心理的にかなり抵抗があったと思います。
配当金の受け取り方を間違えると課税で損をする
ここで少し制度的な話も。
配当金は受け取り方や課税方式によって、手取り額が大きく変わります。
受け取り方法の違い
証券会社で設定できる「株式数比例配分方式」を選んでいれば、証券口座にまとめて配当金が入ります。
これをしておかないと、銀行や郵便局で受け取る方式になり、確定申告での損益通算ができなくなってしまうので注意です。
課税方式の違い
配当金は、原則20.315%(所得税+住民税)の源泉徴収がされます。
ただし、確定申告で課税方式を選べます。
- 申告不要制度:そのまま20.315%で課税
- 総合課税:給与と合算、配当控除を使えるが所得税率によっては逆に損
- 申告分離課税:株式の譲渡益と損益通算できる
僕のように「休職で収入が減った年」は、総合課税+配当控除を選ぶと税金が戻ってくるケースがあります。
一方、年収が高い人は分離課税を選んだ方が有利なことも。
この辺りは人によって最適解が変わるので、毎年シミュレーションして決めるのが重要です。
ライフステージによって変わる「配当金のありがたみ」
今回の休職で痛感したのは、ライフステージによって投資の意味が変わるということです。
- 資産形成期(20〜40代)
→インデックス投資で複利成長を最大化するのが効率的 - 支出がかさむ時期(子供の学費や住宅ローンなど)
→毎月の配当金があると心理的に楽 - 老後期(60代以降)
→年金+配当金で生活が安定、取り崩しストレスなし
つまり、
「資産を増やすエンジン=インデックス投資」
「生活を支えるクッション=高配当株」
と役割を分けて考えると、非常にバランスが良いのだと思います。
まとめ
休職中、毎月の配当金が生活費の3割をカバーしてくれたことで、精神的に本当に救われました。
インデックス投資では得られない「現金の安心感」があるからです。
ただし、高配当株は資産拡大期には効率が悪い部分もあります。
結局は、ライフステージに合わせて投資の比重を変えるのが賢い戦略だと実感しました。
これからも僕は、
- 基本はインデックス投資で資産形成
- 生活防衛や安心感には高配当株
という二本立てで進めていこうと思います。